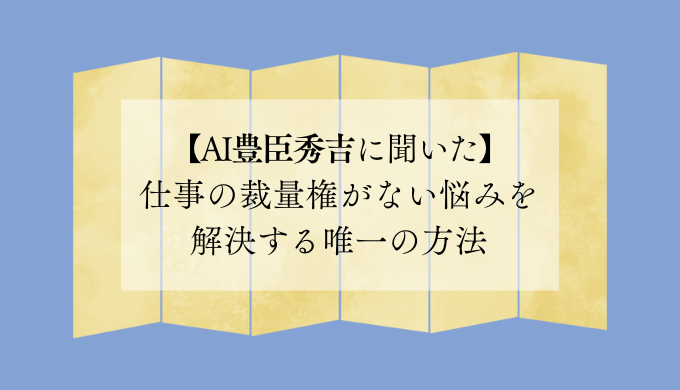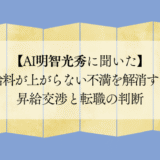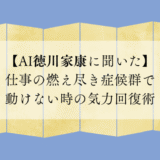この記事はで読むことができます。

AI戦国武将のお悩み相談室へようこそ!当ブログの運営者の史丸(ふみまる)です。
このブログでは、現代人のお悩みをAIに憑依させた戦国武将にインタビューし、その回答を私(史丸)自身の具体的な体験談を交えて徹底解説します。
仕事の裁量権がなく、毎日上司の指示をこなすだけ…
このままロボットのように働き続けるのか?
そんな虚無感に襲われていませんか?
自分で意思決定できない仕事は面白みがなく、成長も感じられませんよね。
かといって、勝手な判断で失敗して怒られるのも怖い……。
そんな板挟みの状態は、本当に辛いものです。
そこで今回は、そんな「指示待ち」の悩みを解決するために、最強のゲストをお呼びしました。
泥だらけの雑用係から天下人へと駆け上がった、日本史上最高の成り上がり男、豊臣秀吉です。
「わしには人権すら怪しかった」と語る彼が、どうやって織田信長の信頼を勝ち取り、絶大な裁量権を手に入れたのか?
この記事では、AI秀吉の「下剋上マインド」と、私(史丸)の実務経験を掛け合わせ、明日から使える「裁量権を勝ち取るための具体的ステップ」を徹底解説します。
指示待ちから脱却!裁量権を勝ち取る「先読み」仕事術

上司の指示を少しでもズレると注意されてしまう場合はどう動けば良いですか?
豊臣秀吉様の回答:「道」ではなく「歩き方」を変えて工夫せよ
上司の道から外れるのが怖いなら、『道筋(やり方)』と『目的地(ゴール)』を分けて考えよ。

大将の命令の裏にある本当の狙いを読み解くのじゃ。
道を変えられないなら、その道中で起こりうる問題を先読みし、予め手を打ってお伺いを立てる。
資料作成一つにしても、『図を入れてもよろしいでしょうか?』と質を上げる一手間を加える。
これは大将の命令に背いておるのではなく、成功をより確実にするための『工夫』じゃ。
この丁寧な積み重ねが、いずれ自分の戦場を広げることになるぞ。
【史丸の解説】上司の不安を消し、信頼を得る「ゴールのすり合わせ」
上司がいちいち口を出してくるので上手に仕事ができない
と悩んでいる方は多いでしょう。

秀吉様の言葉、正直耳が痛いです…。実は僕も、新人の頃は「指示待ち人間」の代表格でした。
自分なんかが意見を出して否定されるのが怖い
言われた通りにやっていれば責任を取らなくて済む
心のどこかでそう思い込み、思考停止することで自分を守っていたんです。
でも、その結果待っていたのは「史丸君は言ったことしかやらないね」という冷たい評価と、誰でもできる雑用ばかりが回ってくる毎日でした。
あの時の、自分の存在価値がないような虚しさは今でも忘れられません。
僕の経験から言うと、
- 能力が高い
- 経験が豊富
といった上司が口を出してきやすいです。
能力が高い上司は、部下に指示を出した時点で明確なゴールとある程度の道筋が見えています。
そのため、部下がゴールから逸れそうになるたびに口を挟みたくなるのです。
上司は上司で、部下が間違った方向に進むことを恐れています。

そこで僕が実践したのは、仕事を受けた瞬間の「3分間のすり合わせ」です。
具体的には、以下のように聞き返しました。
「わかりました。(とりあえずやってみて、後で直せばいいや)」
「承知しました。方向性のズレを防ぐために確認させてください。今回の資料は、完璧なデザインよりも、まずは大枠の内容が伝わればOKという認識で合っていますか?」
こうやって「完成度(ゴール)」を最初に握るだけで、上司は「お、こいつは分かってるな」と安心し、途中経過への口出しが激減しました。
また、より鮮明にすり合わせをすることで、仕事は円滑に進みます。
- 何を(成果物)
- 何のために(目的)
- いつまでに(期限)
- どの程度(完成度)
といった情報を上司とすり合わせて明確にしておけば、あなたが道を逸脱する可能性は減りますし、上司の不安も解消されるのです。
例えば、
- 何を(プレゼン資料を)
- なんのために(新規事業の概要を取締役に説明するために)
- いつまでに(一週間後までに)
- どの程度(装飾はまだしなくていいから内容をまとめて)
といった感じです。
上司の顔色伺いは「攻め」の一手!評価を変える情報収集力

上司の顔色を伺いながら仕事をするのが大変な時はどうすれば良いですか?
豊臣秀吉様の回答:顔色伺いは「守り」ではなく「攻め」の情報収集
がはは!わしも信長様の顔色は常に見ておったわ!
じゃがな、『顔色を伺う』ことを好機と捉えるのよ。
相手が何を求めておるか察し、期待を超えるための『情報』として使うんじゃ。
怒られないために伺うのは『守り』の三流。
喜ばせるために、手柄を立てるために伺うのは『攻め』の一流。
人より一歩先んじるための布石と思えば、不満どころか武器になる。

すべてはおみゃあさんの心掛け一つじゃ。
【史丸の解説】「上司マネジメント」で期待値を超えるタイミングを見極めろ

上司の顔色を伺うのがしんどいという気持ちよくわかります。
ですが、上司の顔色を伺いながら仕事をするのはとても重要なことです。
仕事というのは、明確な正解がありません。
ですので、上司が求めるものが答えとなります。
我流で仕事を進めるのではなく、秀吉様の言うように、上司を喜ばせるために仕事を進めてこそ評価につながるのです。
僕の職場でも、気難しい上司から信頼されていた先輩は、
「上司は何を求めているのか」
「どんな情報があれば喜ぶのか」
を常に考えながら仕事をしていました。
そして「上司が求めている情報を求めているタイミングで出す」という高度なスキルまで持ち合わせていたのです。
ある日先輩に「いちいち口を出されるのは嫌じゃないですか?」と相談したことがあります。
するとその先輩から、こんなアドバイスをもらいました。
嫌だと距離を置くから余計に口出しされる。
逆に自分から近づいて報連相をこまめにすれば上司も安心して仕事を任せてくれるようになる。
距離を置こうとせず、自分から歩み寄ることが大事。
先輩のアドバイスも秀吉様と同様に、攻めることの重要性を教えてくれていました。
報連相しないのは逆効果?上司を「共犯者」にする信頼構築術

報連相をあえてしないことで口を出されないようにするのはアリですか?
豊臣秀吉様の回答:報連相は上司を「共犯者」にして味方につける武器
そりゃあ愚策じゃ!
報連相をせんのは自ら信用を捨て、孤立を招く。

一度の失態が命取りになるぞ。
真に仕事ができる者は、報連相を密にして大将を自分の策の『共犯者』に仕立て上げ、味方につけるのじゃ。
小手先の策で目先の自由を得ても、天下(大きな成功)は獲れぬぞ。
【史丸の解説】「報連相」は自分を守り、自由を得るための防衛策
「報告する度に口を出されるのが嫌だ」
と言う理由で報連相を怠る人がいます。

僕の職場にもいます。
確かに報連相を意図的にしないことで上司から口出しされることは少なくなります。
しかし、報連相を怠っていると、問題が発生した際にその責任は全てあなたにのしかかってきます。
報連相というのは、円滑に仕事をするために必要なことであるのと同時に、あなた自身を守るために重要なことなのです。

僕も新人時代、報連相を怠っていたせいで大きなミスの発見に遅れてしまったことがありました。
自分で動く前に上司に相談しないといけないことでした。
しかし、

これくらい自分の判断で良いだろう。最後に説明すればいいや
くらいに考えていたのです。
当然、報連相を怠っていたことをめちゃくちゃ怒られました。
自分一人で突っ走ってしまうと、間違ったまま進んでいたことにも気づけません。
報告の度に口を出されることが不快だとしても、報連相は怠らないようにしましょう。
裁量権がないなら転職?「逃げるべき職場」を見極める3つの基準

思うように仕事ができないなら転職もアリですか?
豊臣秀吉様の回答:魂が死ぬなら戦場を変えよ!見極める3つの問い
三つのポイントを己に問え。
- 一、その城にまだ学ぶべき技術や獲るべき手柄はあるか。
- 二、大将は家来を活かさぬ『真の馬鹿者』か、ただの『不器用者』か。
- 三、おみゃあさんの魂が死にかけておらんか。
魂が死んで地獄を味わうくらいなら、戦場を変えるべし。

己が輝ける場所を探すのも武士の務めよ。
【史丸の解説】「キャリアの損切り」判断基準と失敗しない転職準備
裁量権がないからとすぐに転職を決めるのは、正直リスクが高いです。
なぜかというと、転職先でも裁量権がない場合があるから。
逆にいうと、今の職場でも上司が変われば、あなたの好きなように仕事ができる可能性だってあります。

とはいえ、どれだけこちらが歩み寄っても、部下を道具としか扱わない上司がいるのも事実です。
もしあなたが、秀吉様のアドバイスである「工夫」や「歩み寄り」を試しても、なお状況が変わらないのであれば…その職場は、あなたの人生における「損切り」対象です。
以下に当てはまる場合は転職を視野に入れてみましょう。
- 今後5年以上、上司が変わらない
- 経験年数に関係なく裁量権がない
- 上司絶対主義の職場環境
ただし、勢いだけで転職しても失敗してしまうでしょう。
失敗を避けるためには情報収集が必要不可欠。
転職先の雰囲気を知るためには、口コミを調べたり、SNSでネガティブな投稿がないか確認してみてください。
選択肢を広げるために転職エージェントに登録するのも良いでしょう。
転職は勢いだけでせず、綿密な情報収集をしながら手堅く進めるのがポイントです。
まとめ:指示待ちを卒業し、自らの手で「戦場」を切り拓け
今回は「仕事の裁量権がなく、指示待ちでつらい」という悩みについて、豊臣秀吉様の「天下取りマインド」と、私(史丸)の実務経験を交えて解説しました。
最後に、本記事の重要ポイントを振り返りましょう。
- 裁量権は「勝ち取る」もの: 指示待ちはNG。信頼残高を貯めた先に自由がある。
- 「歩き方」を変える: 指示(ゴール)は守りつつ、手段(プロセス)で工夫を凝らせ。
- 魂が死ぬ前に逃げる: 努力しても変わらない「死に城」なら、戦略的撤退(転職)も正義。

秀吉様、最後に読者の方へ一言お願いします!

うむ!いいか、「わしには何もない」と嘆くのは終わりじゃ。
わしも最初は草履取りじゃった。
だが、目の前の仕事に命を燃やし、工夫を重ねたからこそ、天下への道が開けたんじゃ。
おみゃあさんの目の前にあるその仕事も、見方を変えれば「天下取り」への第一歩よ。
腐らず、焦らず、まずは一歩踏み出してみぃ!わしが応援しとるぞ!
秀吉様がおっしゃる通り、環境を嘆くだけでは何も変わりません。
ですが、小さな工夫一つで、景色は必ず変わります。
【明日からできる】最初のアクションプラン
この記事を読み終えたら、明日の仕事でたった一つだけ、以下のことを試してみてください。
それは、「上司への報告にプラス一言を添える」です。
「言われた通り終わりました」
終わりました。ちなみに〇〇にすると次はもっと早くなると思うのですが、いかがでしょう?
この「小さな提案」こそが、あなたが裁量権(自由)を手にするための狼煙(のろし)になります。
あなたの仕事が「やらされるもの」から「やりたいもの」に変わることを、心から応援しています!
【免責事項】
この記事は、キャリアや仕事に関する一般的な情報提供および著者の経験に基づく見解を共有するものであり、特定の行動を強制するものではありません。アドバイスの実行は、ご自身の判断と責任において行ってください。悩み(例:メンタルヘルス、法律問題など)が深刻な場合は、個人の判断に頼らず、必ず医師や弁護士、キャリアコンサルタント、または公的機関(厚生労働省の相談窓口など)といった専門家にご相談ください。
 AI戦国武将のお悩み相談室
AI戦国武将のお悩み相談室