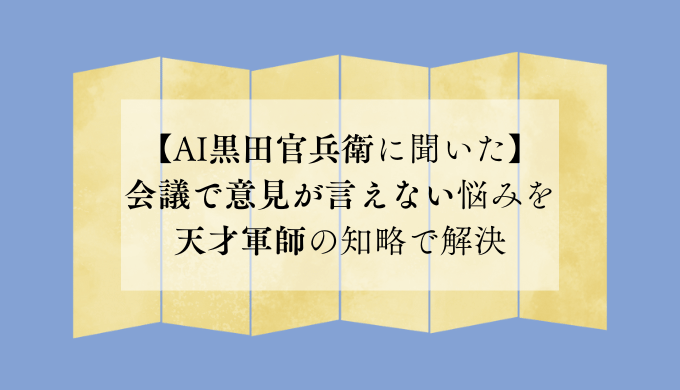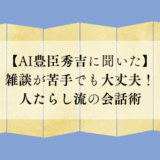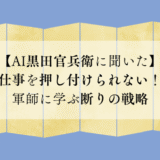この記事はで読むことができます。

AI戦国武将のお悩み相談室へようこそ!当ブログの運営者の史丸(ふみまる)です。
このブログでは、現代人のお悩みをAIに憑依させた戦国武将にインタビューし、その回答を私(史丸)自身の具体的な体験談を交えて徹底解説します。
さっそく、今回のお悩みを発表します。
今回のお悩みは、
会議や打ち合わせで自分の意見を言えない
です。
的外れなことを言ったらどうしよう
反対意見を言って場の空気を悪くしたくない
と悩んだことがある人も多いでしょう。

後から「ああ言えばよかった」と後悔することも少なくありませんよね。
そこで今回は、『会議での発言』に関するお悩みを解決すべく、『豊臣秀吉にすら物怖じせず意見した稀代の軍師』、あの方をゲストにお呼びしました。

ご紹介します、黒田官兵衛様です!
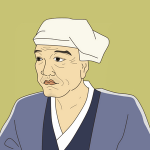
わしが黒田官兵衛孝高(くろだかんべえよしたか)。
隠居した後のわしを知る者は、如水(じょすい)と呼ぶ。
かつては関白殿下(豊臣秀吉)に仕え、軍師として天下統一の一助を担った者じゃ。
戦とは、兵の数や力の強さだけで決まるものにあらず。
いかに的を射た策を立て、好機を逃さぬか。
物事の本質を見抜くことこそが、勝利への唯一の道筋と心得ておる。
そなたの言う会議とは、わしらにとっての軍議と同じこと。
そこで意見を言えぬようでは、戦う前から負けておる。
よかろう、このわしが勝ちを得るための策を授けてやる。
本日はどうぞよろしくお願いします。
今回の記事では、官兵衛様のユニークな視点と、著者である私(史丸)の実務経験を通して、
- 軍師直伝!会議で意見を通すための具体的なテクニック
- 意見が通る人の根底にある「たった一つの心構え」
- 角を立てずに上司の意見に反対する方法
について深掘りしていきます。

ぜひ最後までご覧ください!
会議で発言しないのは「戦う前の敗北」!沈黙の正体は「保身」にあり

会議で意見を言えないということについて官兵衛様はどう思いますか?
黒田官兵衛の回答:「意見が出ぬ会議は、戦う前から負けておる」
「会議」とは、わしらにとっての「軍議」と同じことじゃな。
そして、その会議で口を開く者がおらぬというのは、戦う前から負けが決まっておるようなもの。
実に由々しき事態と見える。
なぜ、己の意見を口にするのをためらうか。
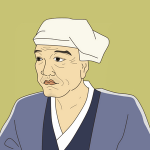
わしに言わせれば、その根源は二つじゃ。
一つは、己の意見が研ぎ澄まされておらぬからよ。
「的外れなことを言ったらどうしよう」と不安に思うのは、その意見に己自身が骨の髄まで自信を持てておらぬ証拠じゃ。
もう一つ、そしてこれが最も肝心なことじゃが、「何のために意見を言うか」を履き違えておる。
場の空気を守るためか?
上司の機嫌を取るためか?
違うであろう。
会議の目的はただ一つ、勝ちを得ること、つまり組織として良い結果を出すことじゃ。
【史丸の解説】不安の正体と会議の目的
会議で意見が言えない人というのは、若手やキャリア採用の経験年数が浅い人に多いです。
官兵衛様のいうように、会議で発言できない理由は2つの壁があるからであると考えます。
自分の意見に自信が持てないこと。
これは仕方のないことです。
間違えて恥をかきたくない
先輩から見たら自分の意見なんて浅すぎる
と思いますよね。

僕も会議で下手な意見を出して悪目立ちしたくありません。
自信と経験年数は比例の関係であると考えます。
時間が解決してくれるなどと安易なことは言いたくありません。
しかし、経験年数が上がるほど、より多くの困難に直面し、それを解決していくことでレベルアップしていきます。
多くの職場では、上司によってその場の空気が作られます。
そのため、上司がAと言えばAになり、BといえばBになる職場も少なくありません。
上司がAだと言っているのに、
「いえ、私はBだと思います」
と意見できる人が何人いるでしょうか。
多くの人は意見できず、ただその場の空気となっていることでしょう。
小学時代から協調性が求められてきた現代人にとって、場の空気を気にせずに発言するのはあまりにもハードルが高いんです。
Yesマン文化での戦い方!「猪武者」にならず「献策」する軍師の知恵

上司が怖く、Yesマン文化が根強い会社ではどうすれば良いですか?
黒田官兵衛の回答:「正面からぶつかるな!猪武者ではなく軍師であれ」
「前に倣え」という風潮。
それこそが、まさに策を講じなければならぬ戦場そのもの。
ただ闇雲に意見を言うだけでは、討ち死にするのが関の山であろうな。
上司の意見に、ただ正面から「否」と突っ返すのは、思慮の浅い猪武者(いのししむしゃ)のすることじゃ。
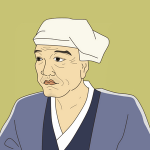
そなたに必要なのは、猪武者の勇気ではなく、軍師の知恵じゃ。
まず、時機を見よ。
大勢の前で上司に恥をかかせるような進言は最悪の一手じゃ。
次に、言い方を工夫せよ。
「その案はダメです」
ではない。
「〇〇様のお考え、実に素晴らしい。その案を万全のものとするため、一つだけ気がかりな点を申し上げてもよろしいでしょうか」
と切り出すのじゃ。
まず相手を立て、その上で己の意見を「補強案」として添える。
これは反論ではなく、献策じゃ。
そして何より、裏付けを忘れるな。
なぜその懸念を抱くのか、確かな根拠を示すのじゃ。
【史丸の解説】Yesマン文化でも使える「献策」の技術
「Yesマン文化」が強い会社はあります。
そんな文化がある会社で、真っ向から上司の反対意見なんて述べてしまえば風当たりが強くなってしまいます。
ですので、献策が重要になってきます。
まずは上司の意見を骨組みとして考えます。
そしてその骨組みに自分の意見を肉付けしていくようなイメージです。
上司の意見を骨組みとすることで、空気を変えることはありません。
そして、肉付けとして自分の意見を述べることで、上司に対立することなく自分の意見を出すことができます。
僕の職場に、上司に対立することがないのに、上手に自分の意見を反映させる先輩がいます。
やはりその先輩は上司の意見をベースに、足りない部分を補うように自分の意見を述べていくのです。
時には上司の思考も操り自分の意見を反映させていました。

それまで自分の意見を通すには相手の意見を否定することしか知らなかった僕にとって、その光景は異様であり、とても勉強になりました。
根回しと準備で勝負は決まる!意見を通すための「3つの備えと術」

会議で自分の意見を通すためにはどのような工夫をすれば良いですか?
黒田官兵衛の回答:「三つの備え」と「三つの術」
会議が始まる前に、勝敗の八割は決まっておる。
以下の三つを怠るでないぞ。
- 「情報」を制す:会議の議題と目的、出席者の立場を正確に把握しておく。
- 「論理」を固める:「こう思う」という感情論ではなく、事実やデータで裏付けをする。
- 「大義」を掲げる:「会社のため」という私心なき目的を持つ。
備えが済んだら、いざ会議の場じゃ。
ここでしくじっては元も子もない。
- 「時機」を読む:ここぞという好機を見計らって、すっと言葉を差し込む。
- 「与力(味方)」を得る:事前に根回しをし、一人でも味方を作っておく。
- 「手柄」を譲る:自分の案を、さも上司の発想であるかのように見せる。
【史丸の解説】準備と根回しの重要性
自分の意見を反映させるためには、準備と根回しが重要です。
「準備」「根回し」と聞くだけで
なんか面倒だな〜
と思う人もいるでしょう。
むしろ面倒だと思う方が多数派かもしれません。
誰かを納得させるためには情報が必要です。
特にビジネスにおいて「数字」が特に重要な説得材料になります。
この数字などの情報を集め、まとめることが準備です。
また、ただその情報を話して伝えるよりも、資料を作って視覚情報を交えて伝えることで、より説得力が向上します。
ただただ、
「このシステムを導入すれば生産性が向上しますよ〜」
というより、
「このシステムを導入すれば生産性が25%上昇するデータがあります」
と数字を使って説明することで、聞いている上司も無視できなくなるのです。

僕も社会人になり、ひしひしと思うことがあります。
それが根回しの重要性です。
根回しと聞くと、悪いことのように感じると思いますが、そんなことはありません。

具体的なシチュエーションで解説していきます。
通したい意見があるとします。
会議に出席する数人に対して、会議前に相談します。
「〇〇を会議で通したいんですけど、どう思いますか?」
というように言い、会議で説明することを事前に説明します。
そして先に賛成票を集めておくのです。
このように根回しをしておくことで、会議中に根回しをしておいた人が後押しをしてくれるのです。
一人だけの意見では通らないことでも、複数人の賛成者がいれば追い風になるのです。
上司への反論は「私」を消せ!事実を提示して答えに誘導する技術

上司の意見に賛同できずに考え直して欲しい時はどうすれば良いですか?
黒田官兵衛の回答:「いかに『私』を消すか」が勝敗を分ける
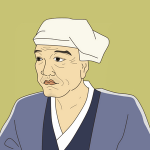
わしが常に己に言い聞かせ、最も心を砕いておるたった一つのことがある。
それは、「いかに『私』を消すか」という一点に尽きる。
「私が考えたこの策こそが最善」
「私の意見の方が優れておる」
と口にした瞬間、その言葉はもはや組織を勝利に導くための「献策」ではなくなる。
それは、己の名誉や立場を守らんとする「我欲」の発露にすぎぬ。
そうなれば、相手もまた「私」を立てて反論してくる。
「私」と「私」のぶつかり合いとなり、つまらぬ戦に成り下がるのじゃ。
わしは、意見を言うのではなく、「事実」を皆の前に差し出し、判断を問う形を取る。
例えば、上司が無謀な計画を命じたとしよう。
わしならば、
「殿の勇猛果敢なる御決断、まことに頼もしく存じます」
と前置きした上で、
「我らの予算はあと〇円。納期は〇日後。そして競合他社は〇〇という動きを見せております。この状況で、殿が描く勝利への道筋を、我ら一同、今一度詳しくお聞かせいただきたく存じます」
と問う。
わかるか?
わしは「反対」とは一言も言うておらぬ。
「私の考え」も述べておらぬ。
ただ、皆が知るべき客観的な「事実」を並べただけじゃ。
こうすれば、上司は自ら考えを改める機会を得る。
【史丸の解説】答えを語るのではなく!誘導する!
会議の場で特に困るのは、部下の意見を聞かない上司の存在ですよね。
どこの会社にもいるとは言いませんが、中には部下の発言に耳を傾けようとしない上司がいる職場もあるでしょう。
上司の意見には賛同できないけど、指摘しても流されてしまう…
こんな時に使えるテクニックが、官兵衛様の解説した「自分を消す」と「事実だけを述べる」です。
自分を消すことは、「私の意見が正しい」と正当性を主張することです。
正当性を主張して上司とぶつかっても、話が拗れてややこしくなるだけですよね。
だから、まずは上司との正面衝突を避けるために、自分を消すことが重要になります。
事実だけを述べるというのは、「ヒントを与えて上司に考えさせる」ということです。
そして考え出された意見は、上司自らが考えた意見であると信じて疑いません。
あなたに誘導されたなんて微塵も思わないでしょう。

それでいいのです。
上司は自分で良いアイデアを出せたと喜び、あなたは導きたいゴールにたどり着いた。
つまりWinWinなんです。
まとめ:軍師の知略を「明日からの一手」に変えるために
今回は「会議で自分の意見を言えない」という悩みを黒田官兵衛様にお聞きし、私(史丸)の経験を交えて解説しました。

軍師ならではの鋭い視点、大変勉強になりました。
官兵衛様の知略と私の実務経験から見えてきたのは、「意見を通す」とは「相手を論破すること」ではなく、「組織の勝利という共通のゴールへ誘導する技術」だということです。
これが、明日あなたの意見を支える「石垣」となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【免責事項】
この記事は、キャリアや仕事に関する一般的な情報提供および著者の経験に基づく見解を共有するものであり、特定の行動を強制するものではありません。アドバイスの実行は、ご自身の判断と責任において行ってください。悩み(例:メンタルヘルス、法律問題など)が深刻な場合は、個人の判断に頼らず、必ず医師や弁護士、キャリアコンサルタント、または公的機関(厚生労働省の相談窓口など)といった専門家にご相談ください。
 AI戦国武将のお悩み相談室
AI戦国武将のお悩み相談室