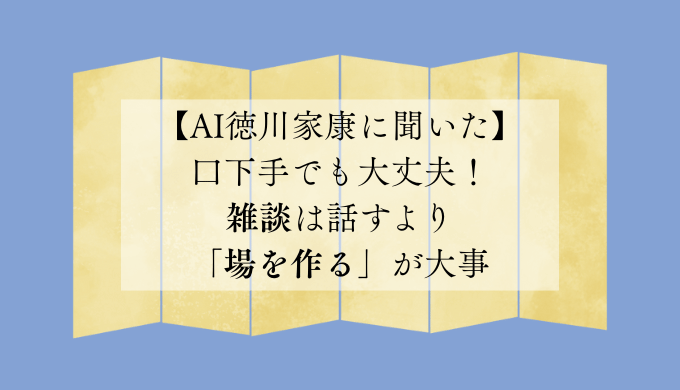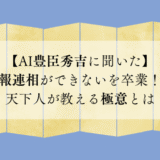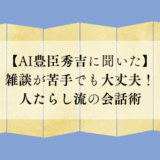この記事はで読むことができます。

AI戦国武将のお悩み相談室へようこそ!当ブログの運営者の史丸(ふみまる)です。
このブログでは、現代人のお悩みをAIに憑依させた戦国武将にインタビューし、その回答を私(史丸)自身の具体的な体験談を交えて徹底解説します。
さっそく、今回のお悩みを発表します。
今回のお悩みは、
雑談やスモールトークが苦手で人間関係を築けない
です。
仕事の話はできても、ランチや休憩時間などの雑談が続かず、気まずい思いをしてしまう
リモートワークの普及で、数少ない雑談の機会を活かせず、同僚との距離が縮まらない
と悩んだことがある人も多いでしょう。

僕自身も、本題に入る前の雑談で何を話していいか分からず、気まずい沈黙が流れてしまった経験があります。
そこで今回は、『雑談や人間関係』に関するお悩みを解決すべく、『忍耐と観察によって天下泰平を成し遂げ、人間関係の本質を見抜いてきた』、あの方をゲストにお呼びしました。

ご紹介します、徳川家康様です!

わしが徳川家康じゃ。
三河の片田舎に生まれ、幼き頃は人質として辛酸をなめ、生涯の半分以上を戦場で過ごしてきた。
織田殿の苛烈さ、豊臣殿の才気。
まばゆいばかりの英雄たちが駆け抜けていくのを、わしはただ、じっと見てきた。
鳴かぬのなら、鳴くまで待つ。
焦りは身を滅ぼす元じゃ。
好機が熟すのをただ待ち、耐え、しのぎ、そうしてようやく天下泰平の世を成すことができた。
派手な勝ち戦ばかりが手柄ではない。
真の強さとは、嵐が過ぎ去ったあとも、変わらずそこに立ち続けている大樹のようなもの。
そのためには、足元を固め、深く根を張ることが肝要じゃと心得ておる。

本日はどうぞよろしくお願いします。
今回の記事では、家康様のユニークな視点と、著者である私(史丸)の実務経験を通して、
- 雑談が苦手な人が抱える根本的な原因(=自分への囚われ)
- 相手の懐に入るための具体的な3つの観察・傾聴ステップ
- 雑談上手のゴールが「面白い人」ではなく「場を作る人」である理由
について深掘りしていきます。

ぜひ最後までご覧ください!
雑談が苦手な人には2つのタイプがいる?徳川家康の分析
徳川家康様の回答:「タイプは違えど、根源は『自分に囚われすぎている』こと」
雑談が苦手な者にはその2つの型が見られるであろう。
じゃが、わしは思う。
その2つは、実は異なる病のようで、根は同じところにある、と。
これは、己のことで頭が一杯で、相手や周りを見る余裕がない者のことじゃ。
戦の前に敵陣をよく見ず、地形も読まずに攻め込むようなもの。
話題など、相手の装いや、場の空気、季節の移ろい、そこかしこに転がっておるわ。
それが見えぬのは、心が己の内ばかりに向いておるからじゃ。
これもまた、己が上手く話さねば、と気負いすぎている者の姿よ。
話を膨らませるのは、己である必要はない。
相手に問いを投げ、相手に語らせればよいのじゃ。
さすれば、相手は心地よく話し、こちらはそれを静かに聞く。

わしは、そうやって多くの者の本心を探ってきた。
つまるところ、2つの型の根底にあるのは、「己に囚われすぎている」という一点に尽きる。
雑談とは、己の弁舌を披露する場ではない。
相手を知り、場の空気を和ませ、次への布石を打つためのもの。
まずはその心を解き放ち、相手に興味を持つことから始めねばなるまい。
【史丸の解説】雑談が苦手な人ほど自分ばかりで相手を見ていない
家康様のご指摘通り、雑談が苦手な人は「自分に囚われすぎている」節があります。
しかしこれは、
場の中で一番面白いことを言ってやろう
というようなものではありません。
自分に自信がないあまり、相手を見る余裕がないのです。
本来、雑談の話題などあってないようなものです。
- 現在の天気や気温
- 外で飛んでいる鳥
- ちょうど見ているニュースの内容
何を話題にしてもいいのです。

僕もよく、目についたものをそのまま話題にしています。
しかし、雑談が苦手な人は話題を難しく考えすぎてしまいます。
この話題で話が続くだろうか
話題がつまらなくて空気を悪くしてしまうのでは?
と考えているうちに、会話の流れについていけなくなってしまうんです。
雑談が苦手な人の中には、
「うん」
「そうなんですね」
などの相槌を打つので精一杯、という人もいます。
そのような人は話すことのハードルが高いんです。
面白くないこと話して場を盛り下げたらどうしよう
と考えてしまうからこそ、話すことができなくなってしまう。
そしてせっかく話を振ってくれたのに、上手に返せなくて自己嫌悪に陥ってしまいます。
「自分に囚われている」とは、つまり「相手を見ていない」ということ?
徳川家康様の回答:「自分の不安ばかり見ていては、相手の顔は見えぬ」
「己に囚われている」とは、心が内へ内へと向いておる状態のことよ。
わしはどう見られておるか
何か面白いことを言わねば
話が途切れたらどうしよう
頭の中が、このような己の不安で満ちておれば、目の前におる相手の姿など、見えるはずもなかろう。
雑談は畑を耕すに似ておる。
下手な百姓は、己が鍬をどう振るうか、己の格好はどうか、そればかりを気にする。
じゃが、良き百姓は、まず土を見る。
この土は乾いておるか、湿っておるか。
石ころはないか。
土の状態を知って、初めて鍬の入れ方が決まるのじゃ。
その「土」こそが、話しておる相手よ。
相手の顔色、声の張り、ちょっとした仕草。
それらをよく見て、相手の心の状態を推し量る。
そうすれば、かけるべき言葉の一つや二つ、自ずと見つかるものじゃ。
己の顔色を窺うのではない。
相手の顔を、心を見るのじゃ。
【史丸の解説】雑談力を上げるにはまず観察力を身につけるべし
家康様のいうことを一言でまとめると、
雑談をするためには、まず相手を観察せよ
ということです。
いきなり上手に雑談ができるようになるなどあり得ません。
たくさんの場数を踏む必要があります。
まず、ファーストステップとしてやるべきことは、「相手を観察すること」です。
会話は相手がいて初めて成立します。
ですので、必ず相手を観察することが必要となります。

僕は子供の頃から、雑談をすることを苦だと感じたことがありませんでした。
話すのが上手いと思っていたくらいです。
しかし、思い返してみると、一人語りばかりしていました。
相手が興味ないことでもひたすら話し続けていたんです。
そのことに気づかされたのは、社会人になってからです。
上司や先輩、他社の方とお話しするようになり、一人語りばかりしていても良好な関係は築けませんでした。
そのため、雑談の方向性を変え、相手を観察するように心がけたのです。
そして相手を観察して話題にすることで、スムーズに会話のキャッチボールができるようになりました。
一見すると、
スラスラ言葉が出る人=雑談力がある
と思いますよね。
ですが僕は様々な人と会話をしてきて、ちょっと違うのではないかと思うようになりました。
というのも、すごく饒舌で1時間でも2時間でも一人で話していられそうな人がいたのですが、周囲の人たちは常に苦笑いを浮かべていたんです。
自分だけ楽しく話をしていても、周りを置いてけぼりにしていては、雑談が上手な人とは言えません。
「相手を見る」ために、具体的に何をすれば良いのか
徳川家康様の回答:「『目で見る』『耳で聴く』『問いを立てる』の三つ」
抽象的な心がけを、具体的な行動に移すことこそが肝要じゃ。
「相手を見る」とは、決して難しいことではない。
わしが長年かけて身につけた、人の見方を三つに分けて教えよう。
話す前から、戦は始まっておる。
相手の様子をそれとなく観察するのじゃ。
- 顔色や装いを見る:今日の相手は、顔色は良いか、疲れてはおらぬか。いつもと違う服や持ち物はないか。「そのネクタイ、良い色じゃな」「少し眠そうじゃが、忙しいのか」など、見たままを口にするだけで、相手への関心を示すことができる。
- 気配を読む: 相手は急いでおるか、それとも時間に余裕がありそうか。場の空気は張り詰めておるか、和やかか。急いでいる者に長話を仕掛けるは愚策。相手の状態に合わせた一言をかけるのが肝心じゃ。
いざ話が始まったら、己が口を開くことよりも、相手の言葉を聴くことに集中せよ。
- 相槌を打ち、続きを促す:「ほう」「なるほど」「それで?」といった短い相槌は、「そなたの話を聴いておるぞ」という印じゃ。相手は安心して話を続けることができる。
- 沈黙を恐れぬ:話が途切れても、焦って次の話題を探すでない。しばしの沈黙は、相手が次に話す言葉を選んでおる時間やもしれぬ。どっしりと構え、待つのじゃ。待てば、相手の思わぬ本心が聞けることもある。
観察し、聴いた内容から、問いを一つ投げかける。
これが雑談の肝じゃ。
- 事実ではなく、気持ちを問う:例えば相手が「昨日、城の改築で難儀した」と申したなら、「大変だったのですね」で終わらせず、「ほう、どのあたりが一番骨が折れましたかな?」と問うてみる。相手が感じた「気持ち」や「苦労」に寄り添うことで、話は自然と深まっていく。
- 自分の話は、問われてから:己の武勇伝や苦労話を長々と語ってはならぬ。相手の話を聴き、「家康殿はどうなのですか?」と問われた時に、初めて少しだけ話すくらいが丁度よい。
これら三つ、つまるところは「関心の矢印を、自分から相手に向ける」ということよ。
【史丸の解説】相手を観察するための3つの心得とは
家康様は、「顔色や装いを見る」「気配を読む」と解説していました。
要するに、観察する場所は「外見」と「内面」があるよ!ということです。
そして、簡単なのは外見を観察することです。
- 着ている服装
- 身につけているアクセサリー
- 髪型
- 化粧
- 持ち物
など、なんでも良いです。
外見は見たそのままなので、観察しやすいのです。
一方、内面は観察するのが難しいです。
世間には、自分の心のうちを隠すのが上手な人がいます。

社会人になって、そのことを痛感しました。
世渡りが上手な人ほど、「本音と建前」を使い分けるのです。
そのような人の内面を、齟齬なく観察するのは非常に難しい。
ですのでまずは、外見から観察していきましょう。
雑談を苦手としている人はよく、
「相槌しかできないんだよね」
と言います。
自分から積極的に会話できないことをコンプレックスに思っているのです。
しかし、相槌が上手な人こそ雑談力がある人だと考えています。
というのも、多くの人は
話したい!聞いてほしい!
と思っている人が多いからです。
自分の話を親身に聞いてくれたら嬉しいですし、ちょっとしたボケでも笑ってくれたら楽しくなります。

僕自身、相槌が上手な人と会話していると、とても気持ちが良いです。
雑談において上手な相槌は武器になるのです。
円滑に雑談ができる人は、適度に質問をしながら会話を回しています。
先ほど説明した「相槌」と「質問」を上手に交えながら会話を組み立てていくのです。
話している側としても、「相槌」と「質問」があれば
話をちゃんと聞いてくれているんだな〜
と嬉しい気持ちになるものです。
上手な質問を適度にすることで、途切れることなくスムーズな雑談ができるのです。
雑談上手は「面白い漫談師」より「話を回すMC」に近い?
徳川家康様の回答:「目指すべきは断じて『MC』。相手こそが主役じゃ」
結論から言えば、目指すべきは断じて「漫談師」ではなく、「現代のMC」のような者じゃ。
「漫談師」は、自分が中心の独り舞台。
自分の話術で人を惹きつけようとする、いわば博打のようなものよ。
話が受ければ満場喝采じゃが、一つ間違えば場は凍りつき、己の浅はかさを晒すだけとなる。
じゃが、「MC」は違う。
彼らの役目は、自分が輝くことではない。
舞台におる者(相手)が、いかに輝くかを考え、話の流れを読み、一人ひとりに気を配り、場全体の調和を創り出すことにある。
茶の湯の亭主を思い浮かべると良い。
亭主の目的は、自分が点てた茶を自慢することではない。
その場に招いた客人(相手)に、いかに心地よい時間を過ごしてもらうか、その一点に心を砕く。
客人こそが、その場の主役なのじゃ。
目指すは、面白い話をする人ではない。
相手が、心地よく話せる場を作る人じゃ。
そこを違えてはならぬぞ。
【史丸の解説】実務で活かす「『名MC』になるための心構え」
雑談が苦手だと思っている人は、起承転結やオチが必要だと考えてしまう節があります。

雑談が苦手だと言っていた友人もオチが難しいと言っていました。
しかし、雑談力にはオチなど必要ないんです。
家康様のいうように目指すべきはオチが完璧な芸人のようなトーク力ではありません。
MCこそがあなたの目指すべき姿です。
家康様からMCというワードが出てくることに少し驚きましたが笑。
まさにテレビにおけるMCのような役回りを上手にこなすことで、雑談に対する悩みは消え去ります。
「僕の話を聞いて!」
「私はこう思っている!」
だけでは、雑談が上手だとは言えません。
独りよがりでしかないのです。
MC、つまり場を回すことができれば、空気を壊すことなく、会話を盛り上げることができます。
そしてMCの面白いところは、常に自分から面白い発言をしなくても、その会話の中心にいられるということです。
誰かの話に適度にツッコミを入れたり、質問を投げかけたりすることで、自ら気張って話を考えなくてもリアクションだけで上手に雑談ができます。
相手が「心地よく話せる場」を作るための具体的なアドバイス
徳川家康様の回答:「堀と石垣(安心感)を固めること」
「心地よい場」を作るは、まさに城を築くが如し。
見栄えの良い天守閣(面白い話)を建てる前に、まずは敵に攻め込まれぬための堀と石垣(安心感)を固めることが肝要じゃ。
まず、自分の心からじゃ。
これが全ての土台となる。
- 勝ち負けを捨てる:雑談は、論争ではない。「何か良いことを言おう」という気負いを、まず捨てよ。
- 裁き心を手放す:相手が言ったことに対して、心の中で「それは違う」と裁いてはならぬ。「ほう、そなたはそう考えるのか」と、ただ事実として受け止める。
- 本物の関心を持つ: これが最も肝心やもしれぬ。「この者は、どのような人間なのか」と、純粋な関心を向けることじゃ。
心が整えば、振る舞いは自ずと変わる。
- 肯定から入る: 相手の言葉を、決して「いや」「しかし」で返すでない。まずは「なるほど」と、一度受け止めるのじゃ。
- ささいな共通点を見出す:どんなに小さなことでも、「同じ」を見つけることで、心の距離はぐっと縮まる。
- 相手の言葉を、そっと繰り返す:相手が「昨日は仕事で難儀してのう」と言えば、「ほう、難儀なことがおありでしたか」と繰り返す。これは「そなたの言葉を、確かに聞き届けたぞ」という証を示すためのもの。
心地よい場とは、「安全な場」のことじゃ。
この人の前では、何を話しても大丈夫だ。
相手にそう感じさせること。
その安心感が、信頼という名の城を築く、最初の石垣となるのじゃ。
【史丸の解説】聞き上手になることで雑談力が身に付く
家康様のアドバイスですが、簡単にいうと、
聞き上手こそが雑談力
ということです。
雑談というと多くの人が「話す」ことに着目し、話術を磨こうとします。
そして聞くことしかできていないことに劣等感を抱いてしまいます。
しかし、実は「聞く」ことこそが雑談力を身につけるうえで重要なんです。
そして、家康様が言うように上手に聞くためには、
- 面白いことを言おうと気張らない
- 相手の言ったことは否定しない
- 相手に関心を持つ
といったことが重要です。
当たり前のようですが、これが難しいんです。
そして、より雑談力を高めるためのプラスアルファとして
- 共感する
- 共通点があることを相手に伝える
- オウム返しをする
が大切です。
家康様は肯定と言いましたが、肯定というよりも共感がより適切な表現だと考えています。
「それわかる!」「それ思った!」と伝えるだけで話している側は気持ちが軽くなるんです。
そして、共通点を見つけたら、「それ私もそうだよ!」「僕もそれ持っているよ!」というように共通点があることを伝えましょう!
また、オウム返しをすることで、「あなたの話をしっかりと聞いているよ!」という意思表示になります。
やってはいけない!雑談における「三つの禁じ手」
徳川家康様の回答:「『裁き』『誇示』『不平』。これらは和を乱す」
物事には、為すべきことと、為してはならぬことがある。
戦に定石と禁じ手があるように、雑談にもまた、決して踏み込んではならぬ道がある。
その場におらぬ者の悪口を言う。
あるいは、目の前の相手の意見を頭ごなしに否定する。
人の悪口は、自分が飲む井戸に毒を投げ込むが如し。
いずれ自分に返ってくるだけでなく、そなたへの信頼をなくすであろう。
自分がいかに優れておるか、いかに大きな手柄を立てたか。
そのような自慢話は、百害あって一利なしじゃ。
「能ある鷹は爪を隠す」と言うであろう。
まことの強者とは、自分の力を誇示せずとも、その振る舞いから自ずと人が認めるものよ。
仕事への不満、世の中への愚痴。
そのような負の言葉は、場の空気を淀ませ、人を遠ざける疫病のようなものじゃ。
誰しも、自分の抱える荷で手一杯。
他人の不平まで背負わされて、愉快な者はおらぬ。
これら三つに共通するのは、いずれも「和」を乱し、人の心を自分から遠ざける行いであるということじゃ。
【史丸の解説】わかっていても、やってしまうから要注意
家康様がおっしゃった『裁き』『誇示』『不平』ですが、
そんな人とは会話したくない!
と思いますよね。
しかし、気付かぬうちに『裁き』『誇示』『不平』が口から出てしまうものなんです。
少し思い出してみてください。
あのとき悪口言ってたな〜
自慢話ばかりしてしまったな〜
久しぶりに友人と会って、職場の不平を吐きまくったな〜
と思い当たる節はありませんでしたか?

恥ずかしながら僕も過去にそんなことを言っていた記憶があります…
無意識に出てしまうものだからこそ、意識して口に出さないように注意が必要なんです。
まとめ:家康に学ぶ「待つ」雑談術と、史丸の「聴く」実践論
今回は、「雑談が苦手」という悩みについてAI徳川家康様にお聞きし、私(史丸)の経験を交えて解説しました。

ご協力いただいた家康様、誠にありがとうございました。
家康様の「自分に囚われるな」「相手を見よ」「場を作れ」という、忍耐と観察に基づく視点は、まさに現代の私たちが忘れがちな本質だと感じます。
今回の学びをまとめます。
- 雑談下手の原因は「スキル不足」ではなく「意識が自分向き」なこと。
- 「漫談師」を目指すな。「MC」のように相手が輝く「安全な場」を作れ。
- 聞き役は強み。武器は「相手の話から拾った、短い問い」で十分。
- 「批判・自慢・不平」は、築いた信頼を一瞬で壊す禁じ手。
家康様は最後に「焦るでない。ゆるりと参れ」と仰っていました。
この言葉を受け、著者である私(史丸)から、読者の皆様が「明日から取り組める具体的なファーストステップ」を一つだけご提案します。
それは、「次の雑談で、自分が話すのを一度こらえ、相手の話から一つだけ『短い質問』をしてみる」ことです。
「〇〇って、どういうことですか?」
「〇〇って、面白いですね」
「もう少し詳しく聞いてもいいですか?」
これだけで構いません。
自分が話すことから、相手の話を「聞く(聴く)」ことへ。
その小さな意識改革が、家康様の言う「信頼の石垣」を築く第一歩になると、私(史丸)は信じています。
この記事が、あなたの悩みを解決する一助となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【免責事項】
この記事は、キャリアや仕事に関する一般的な情報提供および著者の経験に基づく見解を共有するものであり、特定の行動を強制するものではありません。アドバイスの実行は、ご自身の判断と責任において行ってください。悩み(例:メンタルヘルス、法律問題など)が深刻な場合は、個人の判断に頼らず、必ず医師や弁護士、キャリアコンサルタント、または公的機関(厚生労働省の相談窓口など)といった専門家にご相談ください。
 AI戦国武将のお悩み相談室
AI戦国武将のお悩み相談室