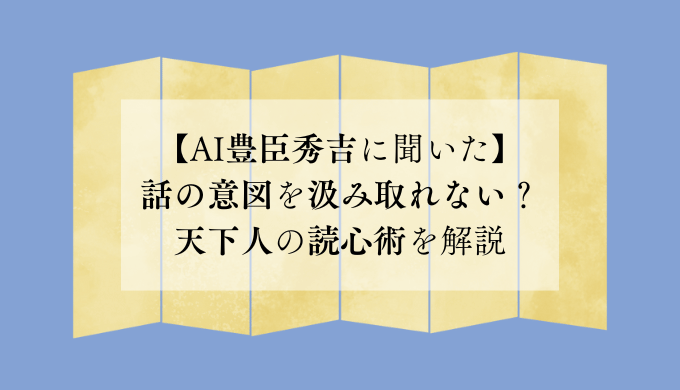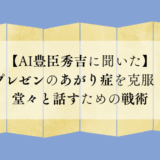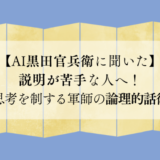この記事はで読むことができます。
AI戦国武将のお悩み相談室へようこそ!

当ブログの運営者の史丸(ふみまる)です。
このブログでは、現代人のお悩みをAIに憑依させた戦国武将にインタビューし、その回答を私(史丸)自身の具体的な体験談を交えて徹底解説します。
さっそく、今回のお悩みを発表します。
今回のお悩みは、
相手の話の意図を汲み取れず、会話が噛み合わない
です。
相手が本当に言いたいことを理解できず、的外れな返答をしてしまう…
一生懸命聞いているつもりでも、「話が通じない」と思われてしまう…
と悩んだことがある人も多いでしょう。

良かれと思って返した言葉が、相手をイライラさせてしまうと、どうしていいか分からなくなりますよね。
そこで今回は、『話の意図を汲み取る方法』に関するお悩みを解決すべく、『農民から天下人へと駆け上がった日本史上随一の出世頭』、あの方をゲストにお呼びしました。

ご紹介します、『豊臣秀吉』様です!

がはははは!おう、わしを呼んだのはお主か!
わしが日の本一(ひのもといち)の出世頭、
豊臣秀吉じゃ!
尾張の貧しい百姓から、あの織田信長様のお草履取りを経て、ついには天下人にまでなった男ぞ。
人の話の意図を汲み取るのに悩んでおるそうじゃな。
任せておけ!
人の心を掴むことにかけて、このわしの右に出る者はおりゃせんわ!
お主の悩みなぞ、この秀吉がぱーっと晴らしてやろうぞ!
本日はどうぞよろしくお願いします。
今回の記事では、秀吉様のユニークな視点と、著者である私(史丸)の実務経験を通して、
- 言葉の裏にある「感情」や「状況」を見抜く視点
- 相手の役割(城)に基づいた「先読み」の技術
- 会話への苦手意識を克服するマインドセット
について深掘りしていきます。
ぜひ最後までご覧ください!
言葉の裏にある「根っこ」を見よ!話の意図が汲み取れない本当の原因

話の意図を汲み取ることが苦手な人が多いのはなぜですか?
豊臣秀吉の回答:「言葉の裏にある『根っこ』を見よ!」
お主が相手の話の意図を汲み取れんのは、
相手の『言葉』だけを律儀に聞こうとしとるからじゃ。
人の話というものはな、野菜みたいなもんよ。
言葉は土から出ている葉っぱの部分じゃ。
じゃが、本当に大事なのは、土の中に隠れておる根っこの部分……
つまり、相手の『感情』や『状況』なんじゃ。

わしは寒い冬の日、主君である信長様の草履を懐(ふところ)で温めておいた。
「草履を温めよ」などと一言も命じられてはおらん。
わしは信長様の『言葉』ではなく、『お体の具合』や『心の疲れ』を読んで、先回りしたんじゃ。
言葉の裏にある、そういった根っこを想像してみるんじゃ。
そうすれば、相手が本当に何を求めているのか、自ずと見えてくるもんじゃぞ。
【史丸の解説】一言一句聞きとる必要はない
秀吉様のおっしゃる通り、話の意図を汲み取るのが苦手な人は、「一言一句逃さずに全て聞こう」としてしまいます。
しかし、これでは脳のリソースを「ただ聞くこと」に費やしてしまいます。
そこでまずは、話のキーワードを探すことを意識してみましょう。
秀吉様はこれを「根っこ」と表現しています。
全て聞き取ろうとする必要はありません。
- 相手が何を伝えたいのか
- どこに共感して欲しいのか
- 何を質問しているのか
上記の項目に当てはまるキーワードを探してみてください。

僕は常にこの項目に当てはめるながら人の話を聞いています。
要するに話の核となる部分を探しながら話を聞いているのです。
「オウム返し」と「二択」で真意を探れ!足軽から天下人まで使える3段階の確認術

Q.仕事において相手の意図を探る具体的な方法は何ですか?
豊臣秀吉の回答:「足軽から天下人までの段階別・探り術」
会話が苦手な者でもできることから順に、探りの入れ方を授けてやろう!
- オウム返しの術:相手が言った言葉の最後を、そのまま繰り返して問い返すだけじゃ。
- 五つの問いの術:「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」を、ただ聞く。
- 味方であると示す術:「成功させたいので、我々が一番気を付けるべき点は何でございましょうか?」と、相手のために聞く姿勢を見せる。
- 二択で迫る術:「早さを優先されますか、それとも丁寧さを優先されますか?」と選ばせる。
- 心を温める術:仕事の前に相手の心身を気遣う。「お疲れではございませんか?」この一言で、相手は心を許す。
- 未来を見せる術:「もしこの仕事がすべて大成功に終わったとしたら、半年後、我々はどのようになっていると思われますか?」と聞き、本当の『目的』を明らかにするのじゃ。
【史丸の解説】意図を汲み取るテクニック
相手の話を聞いただけで意図を理解するのはとても難しいことです。
意図を汲み取るのが上手な人はテクニックを使っているんです。
そのテクニックはまさに秀吉様が示してくれています。
それでは、秀吉様のテクニックを解説します。
オウム返しをすることで、意図をより鮮明に理解することができます。

僕もこのオウム返しを相手から質問された時によく使います。
例えば、
「その時計かっこいいですね!どこで買ったんですか?」
と聞かれたら、
「どこで買ったかですか?旅行に行った際に〇〇店で買ったんですよ〜」
というように相手の質問を繰り返すんです。
質問を繰り返すことで、質問されたことと異なる返答をせずに済みます。
五つの問いは、相手の話をより深く知り、漏れなく意図を汲み取るときに使います。
基本的に話を聞くだけで網羅できることはありません。
「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」を網羅することで、話の意図をほとんど理解できます。
そのため不足している情報を補うために質問するのです。
「それはいつですか?」
とは
「なぜそうなったんですか?」
と質問して情報を網羅していくことで、話の状況がより鮮明に見えてきます。
中級編の中でも僕が特に重要だと思うのは、二択で迫ることです。
二択で迫ることは、相手の指示が漠然としているときに有効です。

相手の話を聞いていて、「どっちなんだろう」と疑問に思うこともありますよね。
例えば、上司から
「この企画書、もう少しインパクトというか、パンチが効いた内容にできないかな?」
と指示されたとします。
この指示だけでは??ですよね。

僕も今まで、上司のふわっとした指示の意図がわからないまま仕事をしていたせいで、上司の求めるものと違う方向に突っ走ってしまったことが幾度となくありました。
一人で突っ走らないためにも、
「新しいアイデアを盛り込んで要素を増やす方向か、逆に要素を削ぎ落として一つの強みを尖らせる方向か、どちらのイメージに近いですか?」
と聞くことで、上司の指示の方向性が明確になります。
このように、相手の指示が漠然としていてよくわかならい場面では、二択の質問をしましょう。
初級・中級ができればあなたはもう十分に意図を汲み取ることができていると言えるでしょう。
秀吉様がおっしゃる上級編は、意図を汲み取ったうえでのプラスワンであると僕は思います。
というのも、上級編は意図のその先にある真意を問うということだからです。
例えば上司が、
「最近チームの空気が緩んでいるから、君の方でもっと厳しく管理してほしいんだ。」
と指示したとします。
それに対して、
「社長から何か言われましたか?」
と聞くのです。
真意とはつまり本音。
「(社長から売り上げを上げるように発破かけられたからどうにかしないとな〜)」
という上司の気持ち、つまり真意を汲み取るのが上級テクニックです。
会話の目的は「完璧な回答」ではない!小さな勝ちを積み重ねる苦手克服法

話を聞くことへの苦手意識を克服するにはどうすれば良いですか?
豊臣秀吉の回答:「目的を変え、小さな勝ちを積み重ねよ!」

その苦手意識は、お主が勝手に作り出しておる、叩けば崩れるほど脆(もろ)い城壁(じょうへき)のようなものじゃぞ。
「完璧な返答をする」という目的を、今日から「相手に、気持ちよく話をしてもらうこと」に変えるんじゃ!完璧を目指すな。
まずは「負けない戦」をすることから始めよ!
「相手の話を最後まで聞けたか?」
→できたなら、勝ちじゃ!
どんな小さなことでも、できたことがあれば、心の中で「えいえい、おう!」と勝ち鬨をあげるんじゃ。
この「勝ち癖」をつけることが、何よりも大事なんじゃ。
いきなり苦手な上司で試すな。
まずは、負けても痛くも痒くもない相手と戦の稽古(けいこ)をするんじゃ。
安全な稽古場で自信をつければ、いざ大事な戦という時に、体が自然と動くようになる。
【史丸の解説】苦手意識は成功体験で克服できる
話を聞くことへの苦手意識は、これまでの失敗からきています。
逆に成功体験が増えれば苦手は克服できます。
簡単に言うけどできたら苦労しないよ!
と突っ込みたくなく気持ちお察しします。
そこで有効な手段を秀吉様が「3つの槌」として解説してくれているのです。
一の槌の「いくさの目的を変えよ」とは、「もっとハードル下げようよ!」と言うことです。
ハードルを下げることで飛び越えやすくなりますからね。

苦手を克服する時はなるべく上を見ずに、スモールステップから始めるように僕も意識しています。
僕は電話を取るのが苦手でした。
それを克服するために、外線は取らずに内線だけ取っていました。
社外からの電話よりも社内からの内線の方がハードルが低いですからね。
内線を取るのが苦じゃないと感じてからは外線も取れるようになりました。
そして二の槌、「小さな勝ち鬨(どき)をあげよ!」は「下げたハードルを飛び越えて成功体験を増やそう」と言うことです。
成功体験を増やしながら少しずつハードルを上げていけばいいのです。
焦る必要はありません。

僕には、思考が完璧主義に寄りすぎている友人がいます。
何をするにも常に目標が高いんです。
目標が高いことは良いことなんですが、すぐ挫折してしまうんです。
僕はその友人にいつも
「最初から完璧にできたらみんなプロになれるよ」
と言って宥めています。
何度も言いますが、焦って最初から高いハードルを越えようとする必要はありません。
まずは自分が楽に越えられる高さにハードルを設定しましょう。
話を聞くのが難しいのであれば、まずは失敗しても大丈夫な相手と練習しましょう。
例えば、
- 仲の良い同期や先輩
- 家族
- AI(Gemini、Chat GPTなど)
との会話の中で意図を汲み取る練習をすることで自信をつけるのです。
別に明後日なことを聞いたとしても、軽蔑されたり問題に発展しないような仲であればいくら失敗しても大丈夫です。
僕も英語の勉強のためにAIと会話をしたりしています。
AIに可笑しな英語を話しても恥をかくことはありませんからね。
悩める者たちよ、よう聞け!
豊臣秀吉の激励
『話の意図が汲み取れぬ』とな?
『人の心が分からぬ』とな?
がははは!めでたい、実にめでたいことじゃわい!
それはな、お主らがこれから、いくらでも強くなれるという証(あかし)じゃ!
「分からぬ」からこそ、人は学ぶんじゃ!
「持たざる者」だからこそ、人の心を掴もうと必死になるんじゃ!
お主らのその悩みは、恥ではない。
それは、お主らを日の本一の人たらしへと押し上げるための、天が与えた好機じゃ!
うつむくでない!胸を張れ!顔を上げよ!
その悩みこそ、お主らをわしと同じ高みへと導く、何よりの宝じゃと知れ!
天下は、人の心を知る者がつかむものよ!
まとめ:言葉の「根っこ」を見る習慣が、信頼関係の第一歩
今回は「相手の話の意図を汲み取れない」という悩みについて、豊臣秀吉様にお聞きし、私(史丸)の経験を交えて解説しました。
農民から天下人へと上り詰めた秀吉様の「人たらし術」には、現代のビジネスにも通じる本質的な知恵が詰まっていましたね。

秀吉様、貴重な金言をありがとうございました。
記事の内容を振り返りましょう。
- 言葉(葉っぱ)にとらわれず、背景にある感情や状況(根っこ)を想像する。
- 相手の役割(城)を知り、「なぜ?」「この後は?」と考えて一歩先を読む。
- 会話の目的を「完璧な理解」から「相手に気持ちよく話してもらうこと」に変える。
そして、この記事を読んだあなたが、明日から取り組める具体的なファーストステップを提案します。
それは、「わからない時は、素直に『オウム返し』で確認する」ことです。
無理に裏を読もうとして深読みしすぎる前に、まずは「〇〇ということでございますね?」と相手の言葉を繰り返して確認してみてください。
これだけで、誤解のリスクは激減し、相手も「話を聞いてくれている」と安心します。
この記事が、あなたのコミュニケーションの悩みを解消し、より良い人間関係を築くきっかけになれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【免責事項】
この記事は、キャリアや仕事に関する一般的な情報提供および著者の経験に基づく見解を共有するものであり、特定の行動を強制するものではありません。アドバイスの実行は、ご自身の判断と責任において行ってください。悩み(例:メンタルヘルス、法律問題など)が深刻な場合は、個人の判断に頼らず、必ず医師や弁護士、キャリアコンサルタント、または公的機関(厚生労働省の相談窓口など)といった専門家にご相談ください。
 AI戦国武将のお悩み相談室
AI戦国武将のお悩み相談室